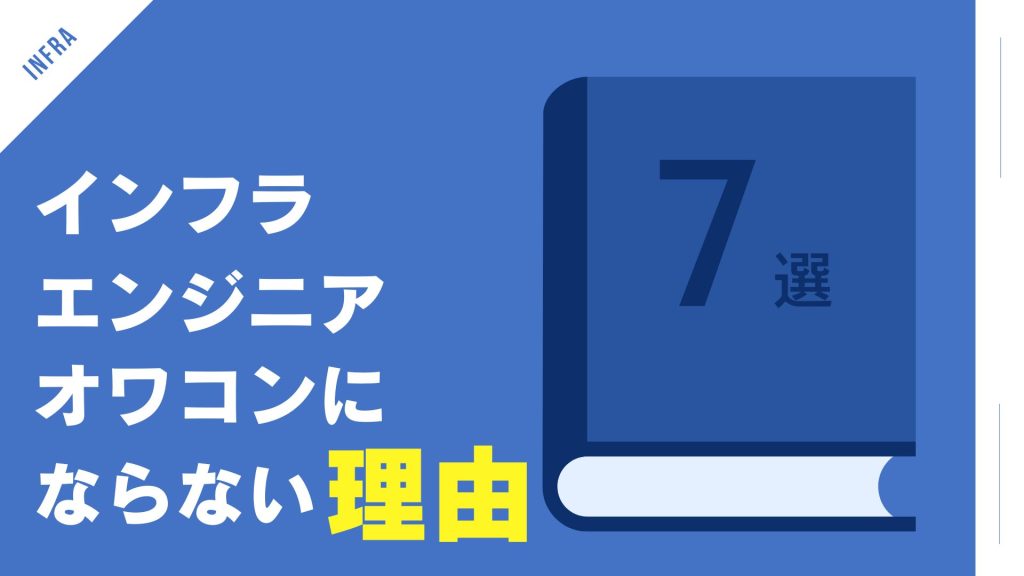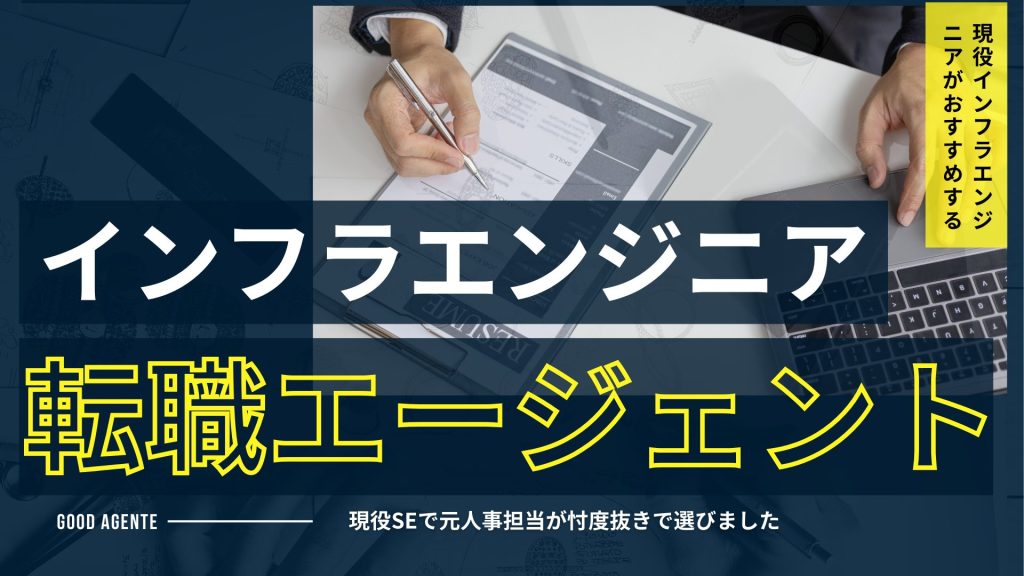この記事で解決できる疑問や悩み
- インフラエンジニアの将来性は明るい?
- クラウド化による影響は?
- 他のIT部分と比較して将来性を確認したい
この記事では、オワコンと噂されるインフラエンジニアについて、深く掘り下げて考えたいと思います。

この記事では、変化の中でどう生き残り、むしろ新たなチャンスをつかめるのかを専門家の視点で深掘りします。
未来はあなたの手にあります。次の一歩を踏み出すために、ぜひ読み進めてください。
目次
インフラエンジニアがオワコンと言われる7つの理由
近年、インフラエンジニアが「オワコン」と言われることが増えています。その背景には、クラウド技術の普及や自動化の進展、業界の変化が大きく関係しています。

この項目では、インフラエンジニアが厳しい立場に置かれていると言われる7つの理由を詳しく解説し、現状を読み解いていきます。
クラウドサービスの普及
クラウドサービスが広く使われるようになり、インフラエンジニアが直接サーバーを管理する仕事が減ってきています。
AmazonのAWSやMicrosoftのAzureなどのクラウドサービスは、簡単にサーバーを利用できる環境を提供します。そのため、企業が自社でサーバーを管理する必要が少なくなっています。

クラウドサービスの普及によって、企業は簡単にサーバーを運用できるようになり、インフラエンジニアの手間が大幅に減っています。
自動化ツールの進化
自動化ツールの進化によって、インフラエンジニアの作業が少なくなっています。
AnsibleやTerraform、Dockerなどの自動化ツールを使えば、手作業でサーバーをセットアップしたり、設定を変更したりする必要がなくなります。これにより、インフラ管理が簡素化されます。

自動化ツールが進化し、インフラエンジニアの作業がより効率的かつ少量で済むようになっています。
DevOpsの普及
DevOpsの導入により、開発者もインフラの一部を担当するようになり、インフラエンジニアの役割が減少しています。
DevOpsは、開発者とインフラ管理者が連携して作業する手法で、開発チームが直接インフラにアクセスし、管理できる体制を作ります。
以前はインフラエンジニアがサーバーを設定していましたが、今では開発者がコードでインフラを構築できます。例えば、コードをプッシュするだけでサーバー設定やアプリのデプロイが自動化されています。
DevOpsにより、インフラの管理が分散され、専任のインフラエンジニアが必要とされる場面が少なくなっています。
コモディティ化
インフラ技術が一般化し、専門知識が求められなくなっています。
インフラ技術が多くの企業で標準化され、特別なスキルや経験が必要とされなくなっています。多くの作業は簡単にできるようになっており、誰でもできるようになりました。

インフラ技術の標準化により、インフラエンジニアの仕事が特別なスキルを要しないものになりつつあります。
サーバーレスアーキテクチャの普及
サーバーレス技術により、サーバーの管理自体が不要になってきています。
サーバーレスアーキテクチャでは、サーバーの運用や管理を考える必要がなく、クラウドプロバイダがすべての管理を行います。インフラエンジニアが手動でサーバーを設定する必要がなくなります。
例えば、AWS Lambdaなどのサーバーレス技術を使えば、プログラムを書いて実行するだけで、どのサーバーで動くかを意識する必要がありません。これにより、サーバーのメンテナンスや運用が不要になります。
サーバーレス技術の普及によって、インフラエンジニアが直接サーバーを管理する機会が減少しています。
コスト削減の圧力
企業はインフラの管理を外部に任せることで、コスト削減を図っています。
クラウドサービスの利用や外注化により、企業はインフラエンジニアを雇用するコストを削減できます。これにより、インフラエンジニアの需要が減少しています。

企業はコスト削減を優先し、インフラ管理を外注化することが一般的になり、インフラエンジニアの職が減少しています。
インフラ以外の領域へのスキル要求
インフラエンジニアは、インフラ以外のスキルも必要になってきています。
インフラエンジニアもアプリケーション開発やセキュリティ、クラウド技術に精通する必要があり、インフラだけでは不十分な時代になっています。

インフラエンジニアも幅広いスキルを求められるようになり、従来のインフラ専業では市場価値が下がっています。
| 原因 | 説明 |
|---|---|
| クラウドサービスの普及 | サーバー管理の簡素化でインフラエンジニアの役割減少 |
| 自動化ツールの進化 | 手作業が減り、効率化されることで需要が低下 |
| DevOpsの普及 | 開発者がインフラ管理を担い、分業が進む |
| コモディティ化 | 専門知識が不要となり、誰でも管理可能な状況 |
| サーバーレス技術の普及 | サーバーの運用が不要になり、管理の手間が削減 |
| コスト削減の圧力 | インフラ管理を外部に任せ、企業がコストを抑える動き |
| 幅広いスキル要求 | インフラ以外の知識も求められ、従来のスキルセットでは不十分 |
全体として、インフラエンジニアの役割は変化しつつあり、従来のように専業で仕事をすることは減ってきています。新しい技術や知識の習得が重要な時代となっています。
インフラエンジニアがオワコンにならないと断言できる7つの理由
インフラエンジニアが「オワコン」と言われることがある一方で、その役割は依然として重要です。クラウドや自動化が進む中でも、インフラエンジニアのスキルと知識は多くの場面で求められています。

この項目では、インフラエンジニアが今後も必要とされ続ける7つの理由を解説し、未来の可能性を探ります。
クラウドサービスの運用最適化が必要
クラウドを使う場合でも、うまく管理しないとお金が無駄になるので、インフラエンジニアは重要です。
クラウドサービスは便利ですが、使い方次第でコストが上がったり、性能が悪くなったりします。インフラエンジニアは、効率的にクラウドを使えるように調整します。

クラウドを効果的に使うために、インフラエンジニアが欠かせない役割を果たします。
インフラエンジニアとクラウドとの関係は、クラウド時代のインフラエンジニアが知るべき今後の展望をご覧ください。
セキュリティ対策の重要性
企業のシステムを守るために、インフラエンジニアはセキュリティの専門家として必要です。
サイバー攻撃が増える中、システムを守るセキュリティ対策がますます重要になっています。インフラエンジニアは、ネットワークやサーバーの安全を確保します。

セキュリティの強化が必要な時代に、インフラエンジニアは不可欠な存在です。
オンプレミス環境の存続
全ての企業がクラウドを使っているわけではなく、インフラエンジニアはオンプレミス環境を支える役割があります。
多くの企業がまだ自社のオンプレミスを使っており、その管理にはインフラエンジニアが必要です。特に、クラウドに移行するリソースがない企業や、特殊な要件がある企業は、オンプレミスを維持しています。

クラウドに移行しない企業のため、インフラエンジニアの仕事はまだまだ必要です。
ハイブリッドクラウドの増加
クラウドと自社のサーバーを組み合わせるハイブリッドクラウドでは、インフラエンジニアの専門知識が重要です。
ハイブリッドクラウドはクラウドとオンプレミスを組み合わせた戦略で、管理にはインフラエンジニアの技術が不可欠です。環境を選び、連携させるスキルが求められます。

ハイブリッドクラウドの導入が進む中で、インフラエンジニアは重要な役割を担っています。
自動化の管理とメンテナンス
自動化ツールを使っても、その設定やメンテナンスにはインフラエンジニアの知識が必要です。
自動化ツールは便利ですが、設定が間違っているとシステム全体が動かなくなることがあります。そのため、インフラエンジニアが正しく設定し、問題が起きたときに対応します。

自動化ツールを使うことで効率化できますが、その管理と保守にはインフラエンジニアが不可欠です。
新技術の導入と統合
新しい技術が次々と登場する中で、インフラエンジニアはその技術を適切に導入し、システムと統合する役割を持っています。
技術の進化に伴い、インフラも変化します。コンテナ技術やネットワーク仮想化などの新しい技術をスムーズに導入するには、インフラエンジニアの専門知識が必要です。
DockerやKubernetesの運用には高度な技術が求められますが、インフラエンジニアが導入し、システムを最適化します。
新しい技術が出るたびに、それを効果的に導入できるインフラエンジニアの役割は重要です。
BCP/DR対策(事業継続計画/災害復旧)
災害が発生しても企業がシステムを復旧できるように、インフラエンジニアは重要な役割を担っています。
自然災害やシステム障害が発生した際に、企業がすぐに業務を再開できるように計画を立てたり、システムの復旧を迅速に行う必要があります。インフラエンジニアはその計画を作成し、実行する専門家です。

災害や障害から企業のシステムを守り、復旧を担うインフラエンジニアは、企業にとって欠かせない存在です。
| 原因 | 説明 |
|---|---|
| クラウド運用の最適化 | クラウドを効果的に使うため、インフラエンジニアの知識が必要 |
| セキュリティ対策 | サイバー攻撃からシステムを守るために不可欠 |
| オンプレミスの存続 | 自社運用のサーバーを管理する役割が残っている |
| ハイブリッドクラウド | 複雑なシステム環境を統合・管理するための専門知識が必要 |
| 自動化の管理 | 自動化ツールのメンテナンスやトラブル対応が重要 |
| 新技術の導入 | コンテナ技術や仮想化などの新技術を取り入れるために必要 |
| BCP/DR対策 | 災害時にシステムを早急に復旧させるための計画と実行が必要 |
これらの理由から、インフラエンジニアの役割はなくならず、むしろ技術の進化に伴い、重要性が増している部分もあります。
雑にまとめると、インフラエンジニアの需要増加は止まらないということですね。
50代以降の現役インフラエンジニアはオワコンになるかもしれない理由
50代以降のインフラエンジニアが「オワコン」と言われる背景には、技術の進化や市場の変化が影響しています。特に、新しい技術の習得や体力面での負担、若手エンジニアの台頭が課題となっています。
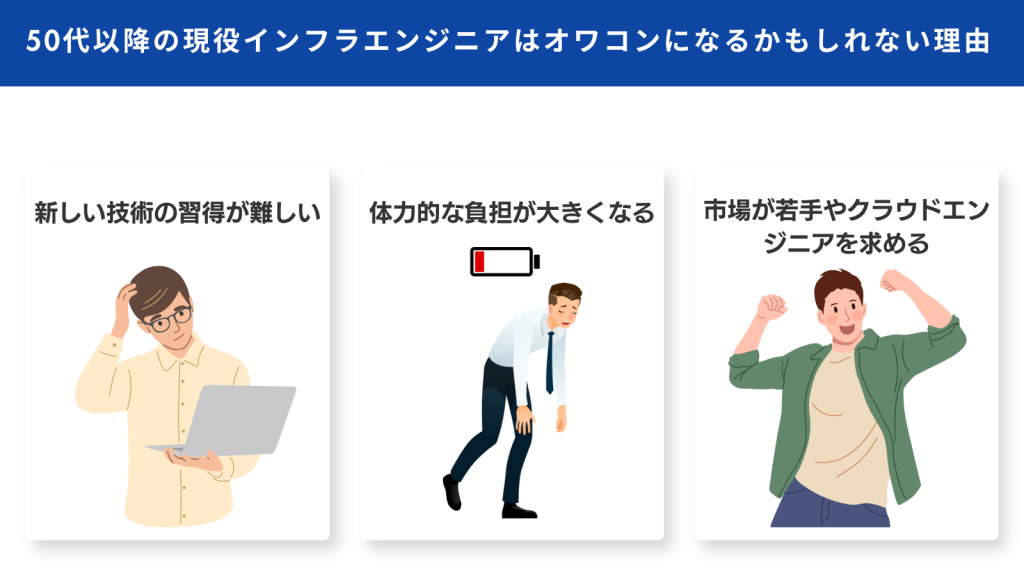
この項目では、そうした理由を3つに絞って詳しく解説します。
新しい技術の習得が難しい場合がある
50代以降のインフラエンジニアがオワコンになるかもしれない理由の一つは、新しい技術を学ぶのが難しくなることです。
IT業界では新しい技術が次々と出てきます。クラウド技術や自動化ツール、コンテナ技術など、最新の技術を学び続ける必要がありますが、年齢を重ねると学習意欲やスピードが落ちる場合があります。

技術の進化が速い業界では、常に新しい知識を習得することが求められるため、50代以降のエンジニアは遅れを取る可能性があります。
体力的な負担が大きくなる
50代以降のインフラエンジニアにとって、体力的な負担が大きくなり、仕事の継続が難しくなることがあります。
インフラエンジニアは、システム障害やトラブルが発生したときに夜間や早朝に対応することがよくあります。これが長時間労働や不規則な作業時間につながり、体力的に厳しく感じることがあります。

体力が求められる仕事のため、50代以降のエンジニアにとっては負担が大きくなり、仕事を続けるのが難しくなることがあります。
市場が若手やクラウドエンジニアを求める傾向
企業は若手やクラウド技術に詳しいエンジニアを求める傾向が強まっており、50代のインフラエンジニアの仕事が減る可能性があります。
クラウド技術の普及で企業は若手やクラウドエンジニアを採用する傾向が強まり、オンプレミス中心の経験を持つ50代のエンジニアは職探しが難しくなる場合があります。

若手やクラウド技術に対応できるエンジニアが求められているため、50代以降のインフラエンジニアは市場での選択肢が狭まる可能性があります。
| 理由 | 説明 |
|---|---|
| 新しい技術の習得が難しい | 最新技術に追いつけず、知識の差が広がる |
| 体力的な負担が大きくなる | 夜間対応や長時間労働が厳しく感じられる |
| 市場が若手やクラウドエンジニアを求める | クラウド技術に特化した若手が優先される傾向 |
50代以降のインフラエンジニアは、技術進化や体力面で厳しい状況に直面しますが、新技術への対応と負担軽減策でキャリアを続ける可能性があります。
年齢に対する不利な面については、インフラエンジニアの年齢制限を打破する方法で詳しくお話ししています。
まとめ
インフラエンジニアは、クラウド技術の普及や自動化の進展により変化が求められていますが、決してオワコンではありません。むしろ、クラウドの最適化やセキュリティ強化、ハイブリッド環境の管理など、新しいスキルが求められ、重要性は増しています。
ただ、常にインフラエンジニアとして市場価値を高める努力は必要です。
50代以降のエンジニアでも、技術習得や体力の負担を工夫すれば活躍の場は広がります。挑戦を続け、変化を恐れずに新しい技術に向き合うことで、未来はまだ大きく開けています。